80種類のおだし


「おだしの文化」を
次の世代につなぐために
海と山の幸に恵まれた日本では
長い歳月をかけ、和食文化の発展にともない
100種を超えるおだしが生み出されてきました。
ところが、昨今では和食離れが進み、
食料品店に並ぶのは
鰹節などの限られたおだしだけで
その多くが姿を消しつつあります。
“おだしの文化を損なわせないために、
様々なおだしの魅力を伝えたい”
そのような想いから、
私たちは日本全国を駆けめぐり、
古今東西、80種類のおだしを集めました。
どれも個性豊かな良品ばかり。
ぜひ、日本の伝統文化を
感じ取ってみてください。


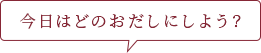

おだしのある生活を
LIFE WITH ODASHI
-

たとえば「お味噌汁」を作るときにも複数の選択肢があります。
鰹と昆布の合わせ出汁にするのか、煮干しにするのか、椎茸にするのか。味噌や具材に合わせておだしを選んだり、複数のおだしをブレンドしたりするのもいいかもしれません。おだしを変えれば料理の風味も変わります。おだしのある生活を楽しんでください。 -

料理に合わせて選んだり、風味で選んだり、調理スタイルで選んだり…おだしの選び方は様々です。
80種類もあってわからない!という方は、お気軽に弊店までお問い合わせくださいませ。おだしコンシェルジュ®があなたにぴったりのおだしをご案内いたします。
おだしの使い方いろいろ
-

煮出して
風味を抽出 -

合わせて
うま味を強める -

ふりかけて
風味を加える -
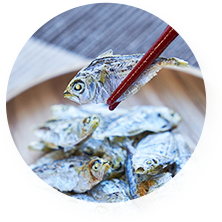
そのまま食べて
栄養を摂る
食材の調理方法・
保存方法から
生まれた
出汁の文化
出汁(だし)の語源は、食材を煮て"うま味"と"香り"を抽出した「煮出し汁(にだしじる)」に由来します。
起源については定かではありませんが、一説では木の実・貝・肉などを煮るようになった縄文時代からだと考えられています。
その後、食材を長期保存するために塩に漬けたり、乾燥させたり、燻製にしたものが現代の出汁の原型になりました。
今日では、煮て燻製にした「節(ふし)」、煮て干した「煮干し」、焼いて干した「焼干し(やきぼし)」などが一般的です。
本格的に
おだしを楽しむ
ENJOY ODASHI
もっとお手軽に
おだしを楽しむ
MORE EASILY
80種類のおだし 一覧
-
 かつお節薄削り(花かつお)
かつお節薄削り(花かつお) 680円(内税)こだわりのかつお節を0.08mmの極薄に削りました。短時間で上質なおだしが取れます。
680円(内税)こだわりのかつお節を0.08mmの極薄に削りました。短時間で上質なおだしが取れます。 -
 さば節といわし節の混合薄削り
さば節といわし節の混合薄削り 720円(内税)鯖(さば)と鰯(いわし)のコクのあるおだし。苦味や雑味が少なく、ふりかけでも食べやすいです。
720円(内税)鯖(さば)と鰯(いわし)のコクのあるおだし。苦味や雑味が少なく、ふりかけでも食べやすいです。 -
 いわし節薄削り
いわし節薄削り 500円(内税)やや濃厚なコクと鰯(いわし)らしいうま味。苦味が少なく、ふりかけでも食べやすいです。
500円(内税)やや濃厚なコクと鰯(いわし)らしいうま味。苦味が少なく、ふりかけでも食べやすいです。 -
 かつお節血合抜き薄削り
かつお節血合抜き薄削り 900円(内税)ワンランク上の上品なかつお出汁がとれます。お吸い物、あんかけ、離乳食にも。
900円(内税)ワンランク上の上品なかつお出汁がとれます。お吸い物、あんかけ、離乳食にも。 -
 かつお本枯節厚削り
かつお本枯節厚削り 840円(内税)存在感のある鰹の香りとうま味のあるおだし。麺つゆやおでんによく合います。
840円(内税)存在感のある鰹の香りとうま味のあるおだし。麺つゆやおでんによく合います。 -
 宗田がつお節厚削り
宗田がつお節厚削り 680円(内税)濃厚なコクとうま味、濃い色のおだし。濃い味つけのうどんや麺つゆに最適です。
680円(内税)濃厚なコクとうま味、濃い色のおだし。濃い味つけのうどんや麺つゆに最適です。 -
 蕎麦だし厚削り
蕎麦だし厚削り 820円(内税)かつお本枯節削りと宗田がつお節削りのブレンドです。香りとコクのバランスの良いおだしがとれます。
820円(内税)かつお本枯節削りと宗田がつお節削りのブレンドです。香りとコクのバランスの良いおだしがとれます。 -
あごの煮干し(とびうおの煮干し)
 650円(内税)九州で定番のおだしです。お味噌汁やお雑煮にどうぞ。
650円(内税)九州で定番のおだしです。お味噌汁やお雑煮にどうぞ。 -
かたくちいわしの煮干し(いりこ)
 650円(内税)日本で一番食べられている煮干しです。お味噌汁や麺つゆに。
650円(内税)日本で一番食べられている煮干しです。お味噌汁や麺つゆに。 -
うるめいわしの煮干し
 600円(内税)脂肪分が少ないので、あっさりしたおだしがとれます。
600円(内税)脂肪分が少ないので、あっさりしたおだしがとれます。 -
ひらこいわしの煮干し
 500円(内税)苦みや魚臭さが少ない、うま味のしっかりしたおだしがとれます。
500円(内税)苦みや魚臭さが少ない、うま味のしっかりしたおだしがとれます。 -
 たいの煮干し
たいの煮干し 650円(内税)甘くて上品なおだしが特徴です。お米と炊けば鯛めしが出来ます。
650円(内税)甘くて上品なおだしが特徴です。お米と炊けば鯛めしが出来ます。




























